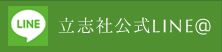2025.07.21
ブログ
祇園祭
こんにちは。
初めまして、立志社の松尾と申します。
今日は京都の夏の風物詩「祇園祭」についてご紹介したいと思います。
7月の京都といえば、やはり祇園祭。1000年以上の歴史を持ち、日本三大祭りの一つとされるこのお祭りは、毎年多くの観光客でにぎわいます。実際に訪れてみて感じた熱気や風情を、写真とともにお届けします。祇園祭は、八坂神社のご祭神「素戔嗚尊(すさのおのみこと)」をお祀りするためのお祭りで、その起源はなんと平安時代の869年にさかのぼります。当時、疫病が流行した際に、人々が神に祈りを捧げたのが始まりとされています。
初めまして、立志社の松尾と申します。
今日は京都の夏の風物詩「祇園祭」についてご紹介したいと思います。
7月の京都といえば、やはり祇園祭。1000年以上の歴史を持ち、日本三大祭りの一つとされるこのお祭りは、毎年多くの観光客でにぎわいます。実際に訪れてみて感じた熱気や風情を、写真とともにお届けします。祇園祭は、八坂神社のご祭神「素戔嗚尊(すさのおのみこと)」をお祀りするためのお祭りで、その起源はなんと平安時代の869年にさかのぼります。当時、疫病が流行した際に、人々が神に祈りを捧げたのが始まりとされています。
宵山(前祭の前:7月14日〜16日)
巡行の前夜にあたるこの期間は、町に立てられた山鉾が間近で見られ、提灯に灯がともり、祇園囃子の音が響き渡ります。町家の軒先では屏風や美術品が展示され、「屏風祭」としても知られています。
巡行の前夜にあたるこの期間は、町に立てられた山鉾が間近で見られ、提灯に灯がともり、祇園囃子の音が響き渡ります。町家の軒先では屏風や美術品が展示され、「屏風祭」としても知られています。
山鉾巡行(前祭:7月17日/後祭:7月24日)
山鉾(やまぼこ)と呼ばれる豪華な曳山(ひきやま)が、京都市内を練り歩く様子はまさに圧巻。装飾には西陣織や海外のタペストリーが使われており、芸術的価値も非常に高いです。
特に「長刀鉾(なぎなたぼこ)」の先頭を歩く稚児(ちご)の姿は人気の的。神の使いとされ、地面を一切踏まないまま輿に乗って登場します。
山鉾(やまぼこ)と呼ばれる豪華な曳山(ひきやま)が、京都市内を練り歩く様子はまさに圧巻。装飾には西陣織や海外のタペストリーが使われており、芸術的価値も非常に高いです。
特に「長刀鉾(なぎなたぼこ)」の先頭を歩く稚児(ちご)の姿は人気の的。神の使いとされ、地面を一切踏まないまま輿に乗って登場します。
祇園祭は、ただの「お祭り」ではなく、京都という町そのものが息づく伝統と文化の象徴だと思います。何百年と続いてきたこの行事には、人々の祈りや想いが込められていて、それが町の景色と一体となって溶け込んでいます。
もしまだ一度も訪れたことがないなら、ぜひ来年は祇園祭を体験してみてください。きっと心に残る夏になるはずです。
もしまだ一度も訪れたことがないなら、ぜひ来年は祇園祭を体験してみてください。きっと心に残る夏になるはずです。